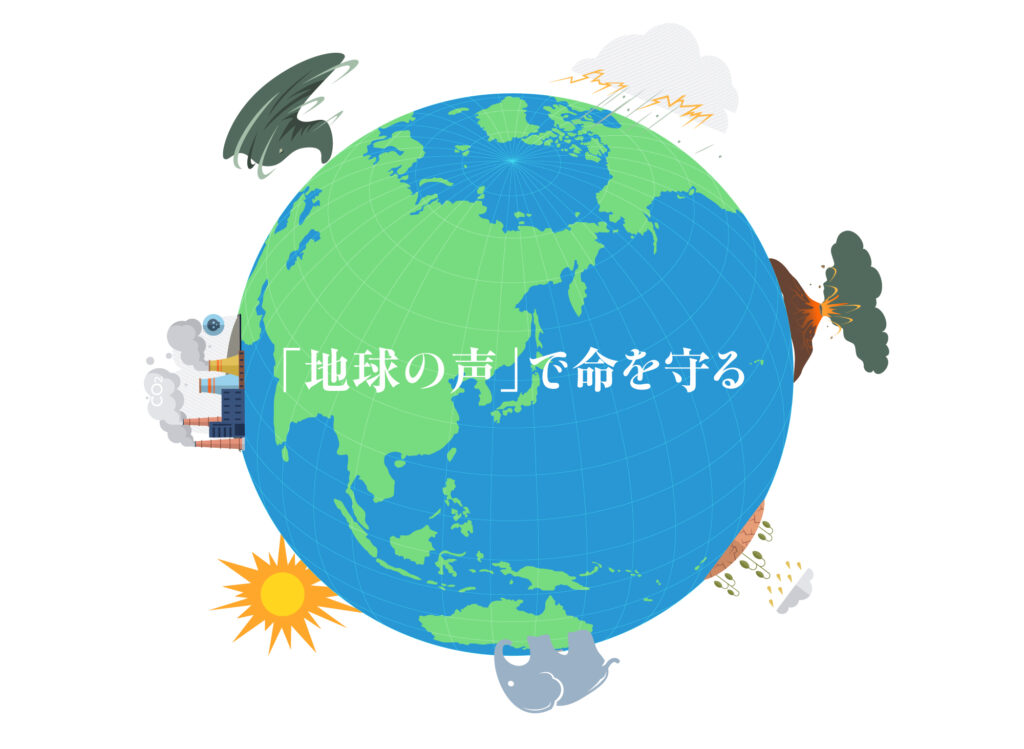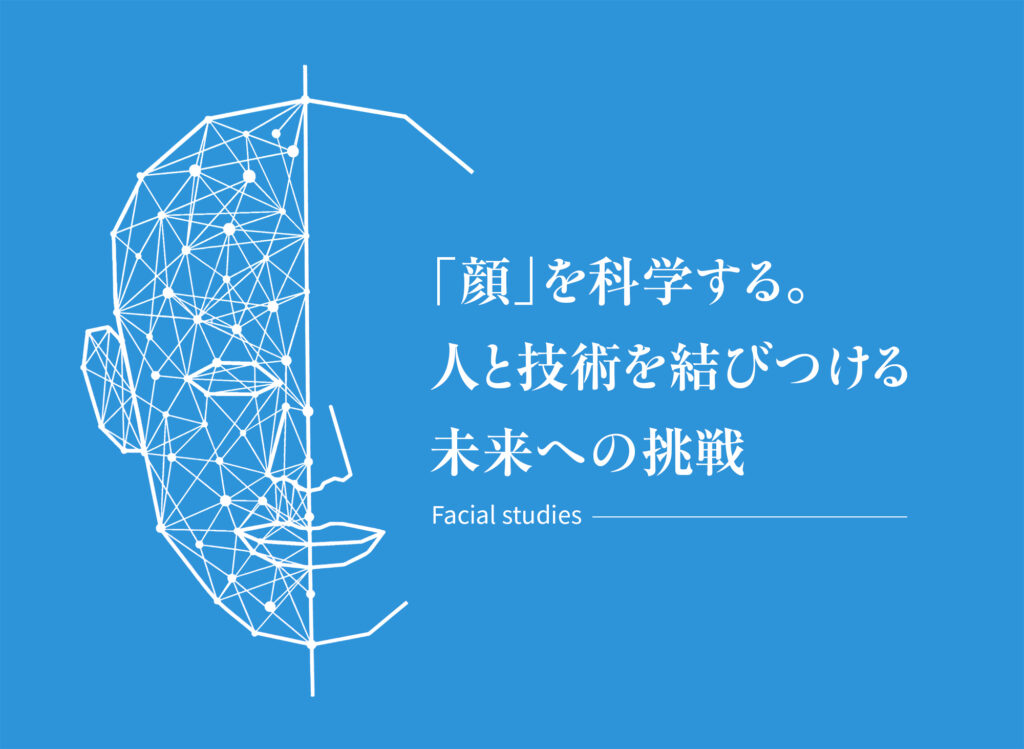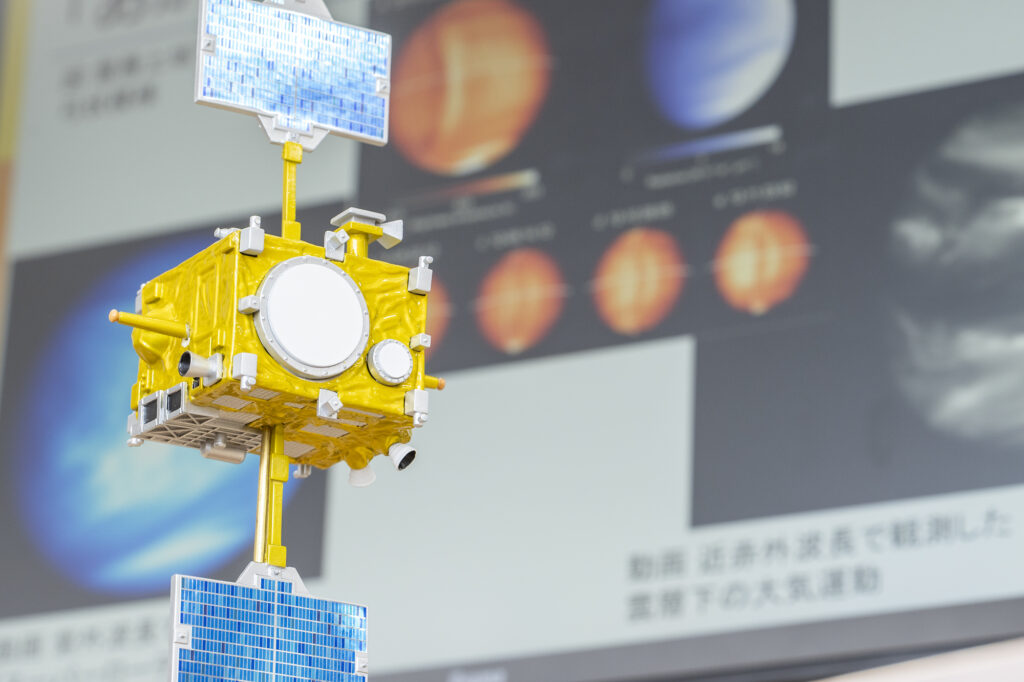日常的な動きから、転倒リスクを検知
日常生活で何気なく行っている「歩行」。そこには健康状態を知る膨大なデータが眠っています。例えば、認知症が進行すると、歩幅が短くなる、歩行速度が低下するなど歩き方の特徴が現れることが知られています。
私の研究では、光学式モーションキャプチャを用いて歩行を解析し、病気の兆候を早期に発見する研究を進めています。
高齢者の転倒事故が急増。死亡者数は交通事故の4倍以上
「歩行」に注目したきっかけは、転倒事故を減らしたいというところからでした。特に高齢者に多い転倒は、単なる事故では済まされない深刻な問題で、骨折やその後の生活の質の低下に直結します。そこで転倒を予防するシステムの開発を考え始めたのが、この研究の出発点です。
注目したのは「ふらつきのある歩行」と「足上げの不足」です。特に高齢になると『足を上げているつもり』でも実際には低く、つまずいてしまう方が多い。つまずきが原因の転倒予防として、手軽に日常の歩き方を監視できる方法としてウェアラブルデバイスでの活用を想定し、限られた手首の動きを利用して足の運動を推測できないかと考えました。
つまり、普段歩いている最中のちょっとした動きから、転倒リスクを検知するということですね。
そうです。さらに機械学習を用いて、歩き方のパターンを捉え、元気のない動きや不安定な歩行の兆候を数値化することを目指しました。この技術によって、歩行状態をリアルタイムでモニタリングし、問題があれば警告を出すことが可能になります。
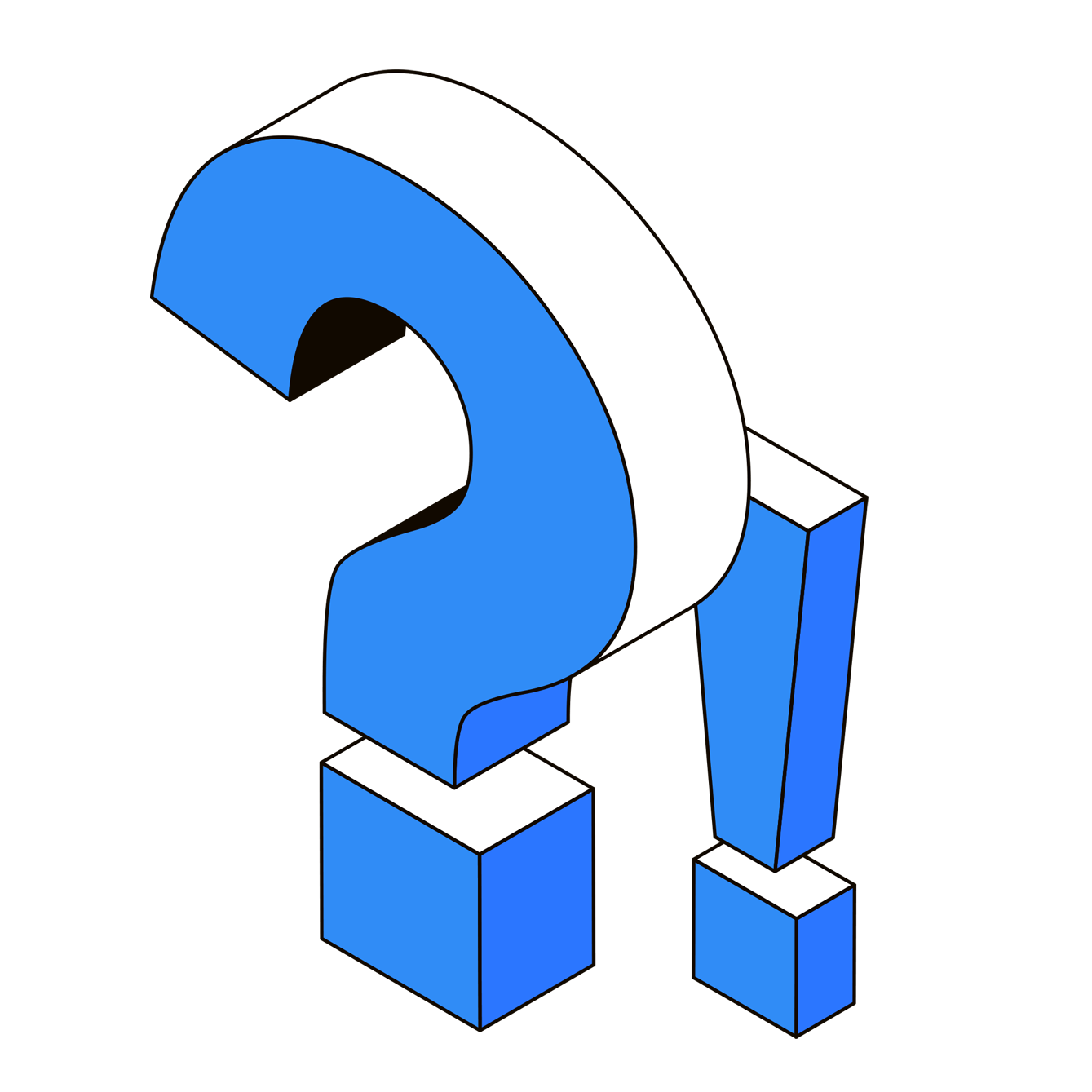 | 身近なスマートフォンを活用した実験 スマートフォンには、動きや向き、明るさ、高さなどを感知するさまざまなセンサーが内蔵されています。たとえば、加速度センサーやジャイロセンサーはスマホの動きや回転を検知し、歩数計・ゲーム・手ぶれ補正に活用されます。また、気圧センサーでは高度が測定できることから、階段昇降を検知するヘルスケアアプリなどに使用されています。 |
転倒防止システムの検討から、病気の兆しをキャッチする研究へ
歩行の「ふらつき」は年齢関係なく、病気の早期兆候や薬の副作用とも関係がある
転倒の原因には、体力の低下や薬の副作用、認知症などの病気による影響などが挙げられます。これらの要因が「歩き方」という行為に現れるのではないかと考えています。たとえば歩行が左右にふらついたり、足の運びに元気がなかったりすることが、病状の早期兆候として捉えられるかもしれません。
歩き方を分析することで、健康状態が分かるということですね。
そうです。これを数値化することで、リハビリや健康管理の効果を見える化することも目指しています。たとえば「最近、体力が向上してきた」「転倒のリスクが減った」といったデータを患者さんやそのご家族に提示することで、安心感を得られるでしょう。
内閣府のムーンショット目標「疾患の超早期予測・予防」の実現へ
内閣府が掲げるムーンショット目標2「2050年までに、超早期に疾患の予測・予防をすることができる社会を実現」に深く関わる研究かと思いますが、実現できるのでしょうか。
たとえば、今はまだ外から見えにくい病気の1つである「認知症」の初期段階などを歩き方から検出することができれば、適切な処置を早く始めて進行を遅らせることができます。そうしたことが技術的に実現できれば、社会全体の健康寿命を大きく伸ばせるでしょう。
これまで感覚的にしか捉えられなかったものが数値として提示され、医学的な裏付けができるようになる。そうすると、医療関係者や患者さん自身の健康管理への意識も変わってくるのではないでしょうか。
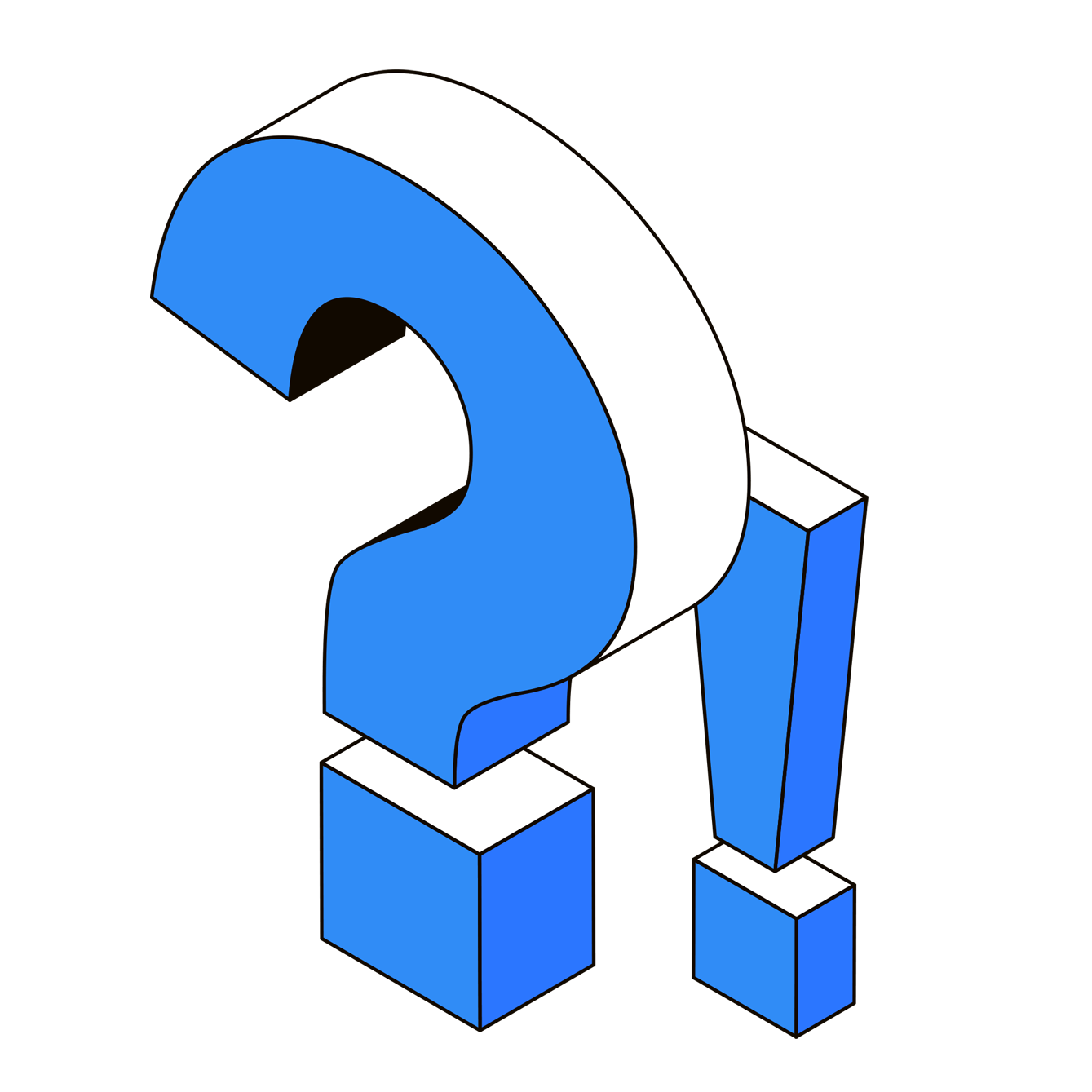 | ムーンショット目標とは? “ムーンショット”とは、アポロ計画(月面着陸)を指す言葉で、「実現が困難でも、成功すれば社会に大きな変革をもたらす大胆な挑戦」を意味します。内閣府が掲げるムーンショット目標では、2050年を見据えて「人々の幸福(Human Well-being)の実現」を目指す国家プロジェクトとし、暮らしの基盤となる「社会」「環境」「経済」の3つの領域から、具体的な10個のムーンショット目標を定めています。 内閣府:ムーンショット目標 |
スポーツやリハビリの現場、さまざまな分野で活用できる可能性を秘めた研究データ
実際にスポーツ科学や福祉工学の先生方と共同研究を進めています。歩行データだけではなく、運動全般のデータを長期間にわたって収集し、ビッグデータとして解析しています。このようなデータを利用すれば、スポーツやリハビリの現場でも新たな発見が期待できるでしょう。
また、歩行のリズムや体の傾き・手の振り方などが、ほかの健康要因とどのように関連しているかを調べることで、新たな知見が得られる可能性があります。他分野の研究者が私たちのデータを見て、別の視点から新しい発見につながるかもしれません。
| 本学の健康情報科学研究センターでは、江別市民1,200人を対象に、10年間にわたり採血や認知機能、心身の健康状態の検査と合わせて、関節の角度、重心の動き、歩行周期などの歩行データを収集。これらのデータからAIの機械学習を活用し、体力レベルや疾病の兆候、認知症の初期サインや服薬の影響など、健康状態の微細な変化を高精度で識別する、新手法の確立を目指しています。 |
歩行データが描く未来の健康地図
パーソナライズ化するデジタルヘルス
今後は、さらに多様なデータを取り込んでいきたいと考えています。たとえばDNA解析と歩行データを組み合わせて、遺伝的な要因との関連性を探ることができるかもしれません。また、IoT技術を活用して、個人が日常的に健康データをモニタリングできるようなシステムをつくることも視野に入れています。
そうなると、ヘルスケアが今よりもっと手軽で身近なものになりますね。
はい。特に高齢者だけでなく、若い世代にも役立つ技術として普及することを目指しています。たとえば運動が足りているのかどうか、適切なリハビリができているのかといった情報を、日常的に確認できる社会をつくりたいですね。
メッセージ
「歩く」という行為は、人間らしさを象徴するものです。私たちの研究は、この歩き方の分析を通じて、人々の健康や生活の質を向上させることを目指しています。未来の社会では、自分の健康状態をより正確に把握し、適切な対策を取ることが当たり前になるでしょう。そのための第一歩として、私たちの研究が貢献できることを願っています。
※所属・役職などはインタビュー当時の情報となります。