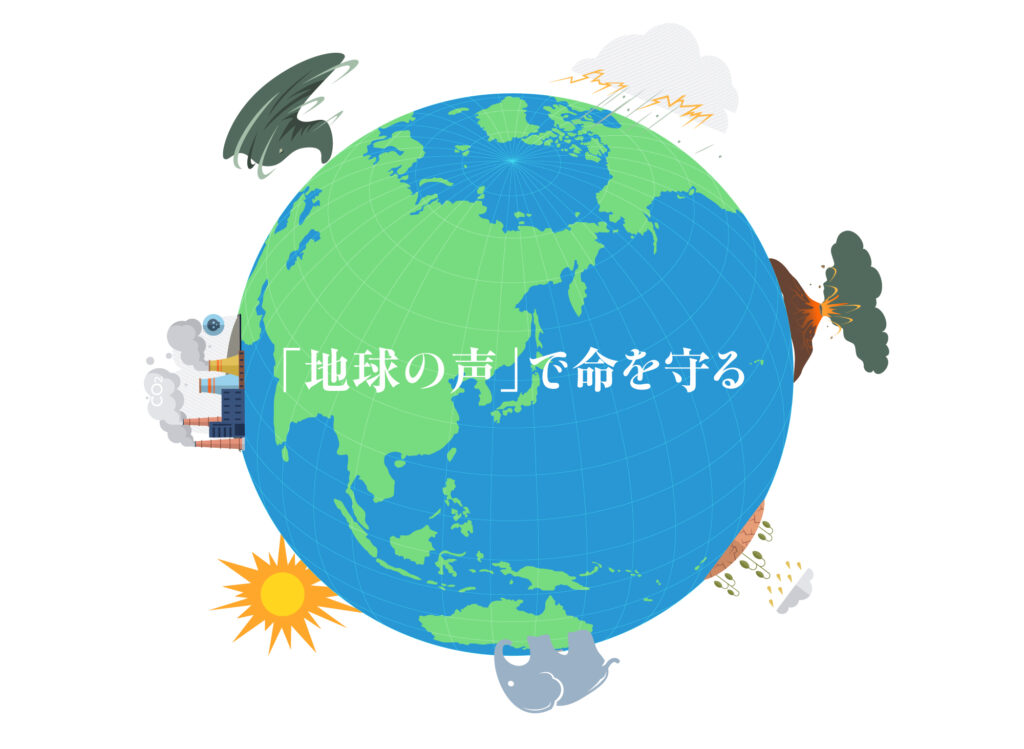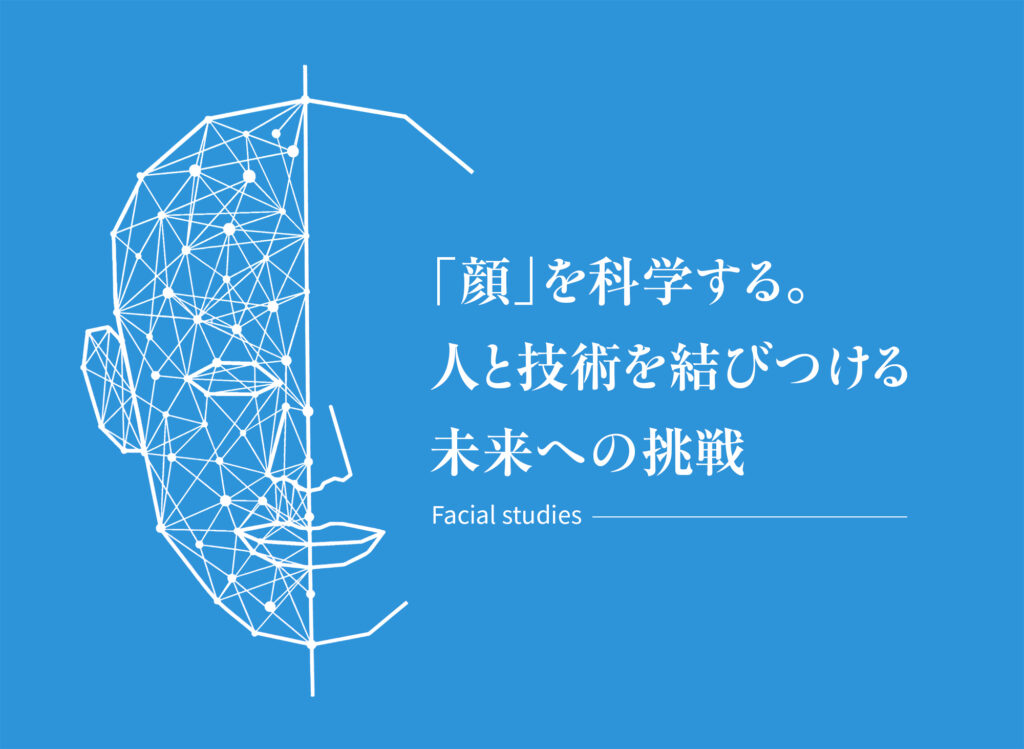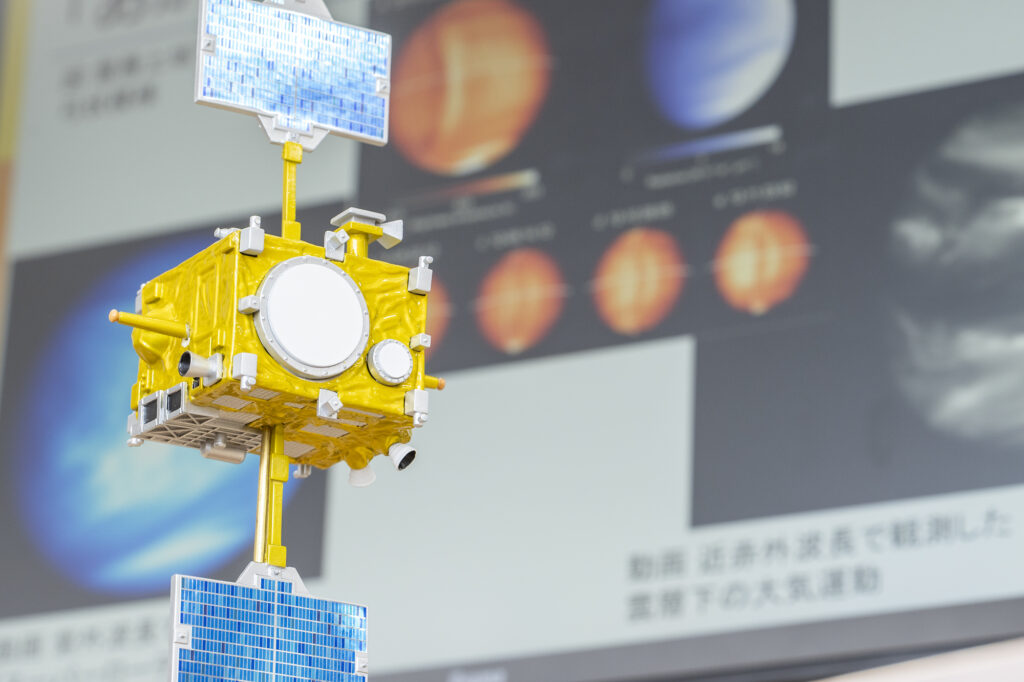空間インタラクションとは?人間とコンピュータの関係性を研究
「空間インタラクション」とはどんな研究?
空間インタラクションとは、空間を経由して人間やコンピュータの関係性が生まれることを研究する分野です。コンピュータを使う際にはキーボードやマウスを使いますが、それらはボタンを押下したり、デバイスを移動することで信号が入力されます。それ以外にも音声やジェスチャー、触覚など、さまざまな操作手段があり、情報の伝達手段として空間の変化を活用しています。
バーチャル空間と物理空間をつなぐさまざまな操作手段
新たな操作手法としてドローンをジェスチャーで操作できるシステムなどを開発しています。また、VTuberの動作に連動して頭を撫でるデバイスを開発・研究しています。この研究では「ペルチェ素子」というデバイスを使って擬似的に触覚を再現しています。動画コンテンツを見ているときに触覚を感じられる技術なんて、まるでSFのようですよね。
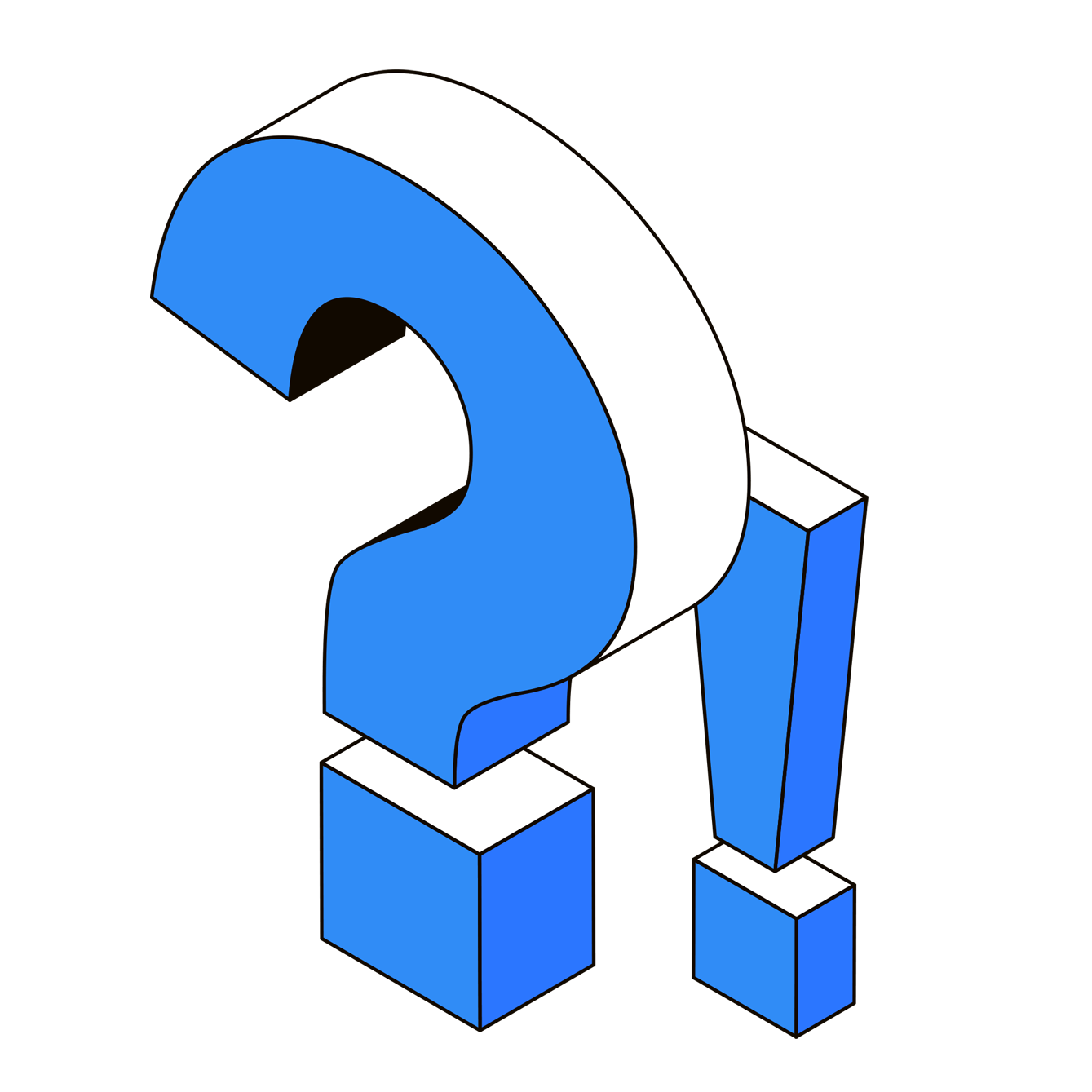 | ペルチェ素子とは? ある方向に電流を流すことで一方の面を冷却し、もう一方の面を加熱する半導体素子のことです。 電流の向きを変えるだけで、冷却と加熱を切り替えることができます。身近なところでは、ネッククーラーや除湿機などにも使われています。 |
本当にSF世界のようですね。その広がりは物理空間だけでなく、バーチャル空間にも及ぶんですね。
その通りです。私たちは「空間」という言葉を幅広く捉えています。物理空間だけではなく、バーチャル空間を活用することで、現実にない新しい体験を生み出せます。たとえば、遠隔地にいる人同士がまるで同じ部屋にいるような感覚を共有したり、バーチャル空間でリアルな感覚を伴うインタラクションが可能になったりします。こうした技術は、私たちの生活やコミュニケーションのあり方そのものを変える可能性を秘めているのです。
学生の自由な発想と好奇心が生む新技術

さまざまな研究テーマに取り組める研究室
研究室では、学生それぞれが自分の興味や経験を活かしてテーマを設定しています。たとえば、バイクが好きな学生はライダー向けのインタフェースを研究しています。
また、エレクトーンを長年習っていた学生は、演奏をリアルタイムで分析して上達を支援するシステムを開発しています。このシステムを使用することで、演奏者自らのパフォーマンスをその場で分析し、フィードバックを得られます。こうしたプロジェクトは、学生たちの個性やバックグラウンドが色濃く反映されていますね。
学生一人ひとりの個性が研究テーマに活かされているのは、とても魅力的ですね。
そうですね。学生の元々の興味に、ARやプロジェクションマッピングといった技術を組み合わせてプロジェクトが生まれています。学生たちの自由な発想や好奇心が、新しい技術やアイデアを生み出しているんです。彼らのアイデアは私の想像を超えるものばかりなので、非常に刺激を受けますね。
コンピュータが人間に寄り添う時代へ
身体への負担がない、新しい形のコンピュータ
2050年、コンピュータがもっと人間に寄り添う形に進化していると考えています。現在多く使われているキーボードやマウスといったインターフェースは、一見便利で生活に馴染んでいるようですが、必ずしも人間に負担がないとは言えません。今後は、身体の動きや感覚に基づいたインターフェースが普及し、コンピュータがより自然に人間の身体や生活に溶け込んでいくでしょう。
具体的にはどのような技術が考えられますか?
視覚情報を眼鏡型ディスプレイで取得したり、ウェアラブルデバイスを使って歩きながらでも安全に情報を確認できるような技術が挙げられます。また、触覚や温感を再現する技術を組み合わせることで、バーチャル空間での体験が現実のように感じられるようになります。こうした技術が普及することで、仕事やエンターテインメント、医療、教育など、さまざまな場面での利便性が向上するでしょう。

情報大ならではの強み
情報大の一番の魅力は、多様な専門分野を持つ教員や学生が集まるユニークな環境です。特に情報メディア学科では、プログラミングやテクノロジーだけではなく、デザインや映像、音楽など幅広い分野を学べます。このように異分野が交差する環境が、新しい発想を生み出す土壌になっているんです。
異分野が交差することで、新しいアイデアが生まれる可能性が広がりそうですね。
その通りです。各分野の専門知識をもつ学生が協力してプロジェクトを進めることで、より多様な研究成果が生まれています。このような環境で、未来の可能性を学生たちと一緒に切り拓いていけることは、私にとって非常にやりがいのあることです。
高校生へメッセージ
これからの時代、テクノロジーはますます人間の生活に寄り添い、生活の質を向上させる重要な役割を果たしていきます。そのためには、既存の常識にとらわれない発想や好奇心が必要です。未来の技術や社会を形作るのは、今を生きる私たち、そしてこれから学びを深める皆さんです。一緒に新しい未来を創造していきましょう。
※所属・役職などはインタビュー当時の情報となります。